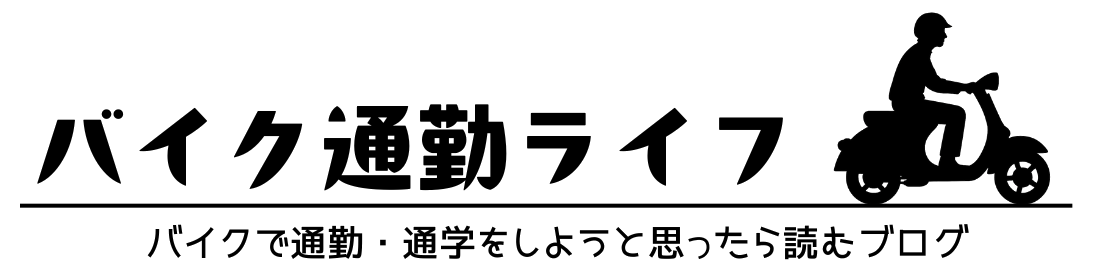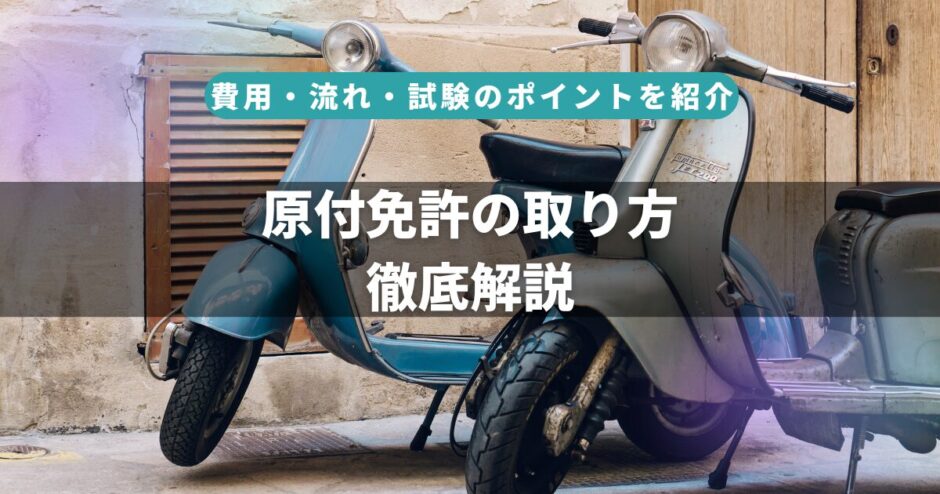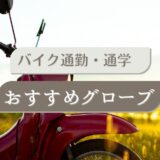この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「通学や通勤に便利な原付(50cc以下)に乗りたいけど、どうやって免許を取ればいいの?」
そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
原付免許は最も手軽に取得できる二輪免許で、16歳以上ならチャレンジできます。

僕は高校卒業後に原付一種の免許を取得して、ヤマハのビーノで大学に通学していました。
普通自動車免許を取得すれば原付バイク(50cc以下)を運転することができますが、今回は原付免許を単独で取得する方法について紹介します。
この記事では、原付一種免許の取得方法、費用、試験の流れ、合格のコツまで、初心者でもわかりやすく解説します。
これを読めば、あなたも原付デビューの第一歩を踏み出せるはずです!
原付一種免許とは

原付一種の免許(正式には原動機付自転車免許)は、排気量が50cc以下、もしくは排気量が125cc以下で最高出力4.0kW以下の二輪車を運転できる免許です。
実技試験は不要で学科試験に合格するだけで取得できます。
原付免許の受験資格は、以下のような条件があります。
- 年齢:満16歳以上
- 現住所:受験する都道府県内に住民登録があること
- 視力:両眼で0.5以上(眼鏡やコンタクトレンズ使用可)
- 色覚:赤・青・黄を識別できること
- 聴力:10メートル以上離れた場所から90デシベルの音が聞き取れること
原付免許を取得するまでの流れ
原付免許を取得するまでの大まかな流れを紹介します。
お住まいの地域によって多少の違いがありますがご容赦ください。
お住まいの地域の運転免許試験場の予約サイトで受験の予約をします。
インターネット環境のない方は、運転免許センターまたは警察署の窓口で予約ができる場合があります。
- 本籍地記載の住民票(6ヶ月以内発行、コピー不可)
- 申請用写真(運転免許試験場で撮影できる場合もあり)
- 身分証明書(健康保険証、パスポート、マイナンバーカードなど)
- 筆記用具
- 必要な方はメガネやコンタクトレンズ
- 手数料:8,050円(試験手数料1,500円、交付手数料2,050円、原付講習手数料4,500円)
参考:https://www.jmpsa.or.jp/safety/license/gentsuki.html
※地域によって異なる場合があります。
申請書に必要事項を記入し、証紙を購入して手数料を支払います。
視力検査や色彩識別を行います。
- 試験内容
交通ルールやマナーについて問う試験です。
・文章問題:46問(1問1点)
・イラスト問題:2問(1問2点、イラストごとに複数設問あり)
合計48問で、満点は50点です。 - 合格基準
50点満点中45点以上(90%以上)で合格となります。 - 試験形式
すべてマークシート方式の○×(正誤)問題です。 - 制限時間
30分です。
合格者はそのまま次のステップへ進みます。
実際に原付バイクに乗る実技講習(3時間程度)。
長袖・長ズボン・運動靴など運転に適した服装が必要です。
原付講習修了後、当日または後日、免許証が交付されます。
学科試験の勉強法
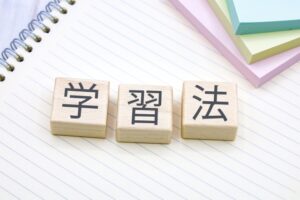
原付免許の学科試験は、交通ルールや標識、マナーなどが出題されます。
○×問題なので難しい内容ではありませんが、引っかけ問題もあるので事前学習が大切です。
原付免許の学科試験は、48問の問題が出題され、45点以上の得点が必要です。
内訳は、文章問題が46問(1問1点)、イラスト問題が2問(1問2点)となっています。
試験時間は30分と限られているため、時間配分を考えながら問題を解くことが重要です。
原付一種の免許を取得するための勉強は、書籍を読んで勉強するのがおすすめです。
テキストは1冊で十分なので、繰り返し読んで内容を覚えましょう。
勉強期間は、2~3日間を確保して集中して勉強することが理想です。
そして、とにかく多くの問題を解くことが一発合格のコツです。
仕上げにスマートフォンのアプリやインターネット上の模擬試験で理解度のチェックをしておくと安心です。
まとめ
原付一種免許は、16歳以上なら誰でも比較的簡単に取得できる便利な免許です。
学科試験のみで取得でき、講習も含めて1日で完了するケースが多いので、すぐに通学・通勤に役立てることができます。
バイクが運転できれば行動範囲が一気に広がりますので、ぜひチャレンジしてみてください!