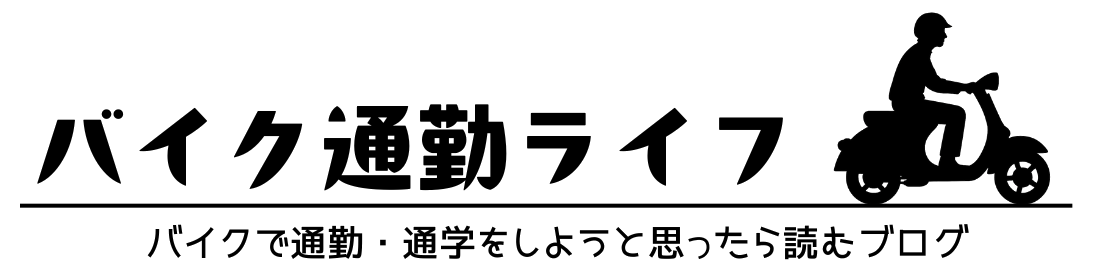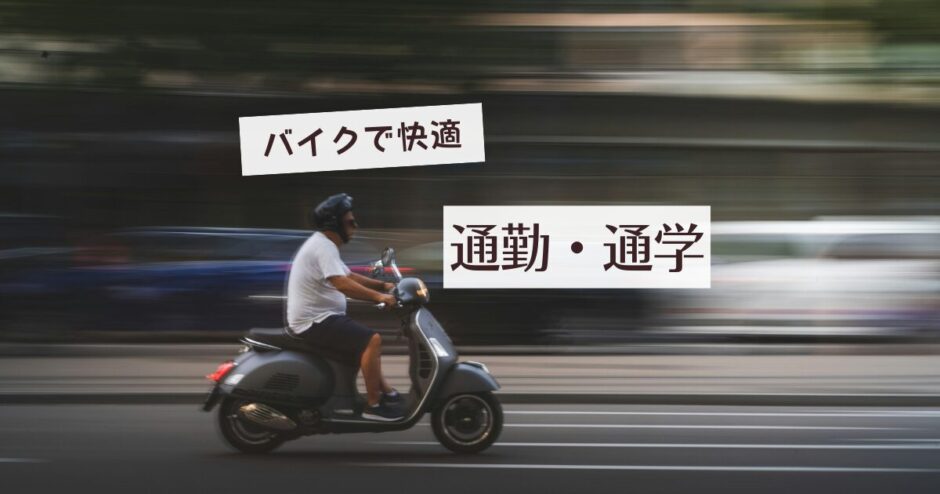この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「バイクで通勤・通学したいけど、何から始めればいいか分からない…」
初めてバイクで通勤・通学しようと思っても悩むポイントはいろいろあります。
そんなあなたのために、現在進行形でバイク通勤をしている僕が、バイク通勤・通学を始めるためのステップを4つに分けてわかりやすく解説します。
- 原付一種・原付二種の特徴と必要な免許
- バイク通勤に向いているおすすめ車種
- 必要な保険の種類と加入方法
- 必要な装備・グッズ
この記事の手順に沿って準備すれば、誰でもバイク通勤・通学を始められます!
ステップ①:必要な免許を取得しよう

バイク通勤には、小型で取り回しやすく、維持費の安い原付一種や原付二種がおすすめです。
それぞれの特徴と、必要な免許について見ていきましょう。
原付一種の特徴
原付一種は、排気量50cc以下(電動機の場合は定格出力0.6kW以下)の二輪車が該当します。
2025年4月からは、新たに「排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下」の二輪車も原付一種として追加されることになりました。
法定速度は時速30kmまでとなっていたり、片側3車線以上の道路の交差点を右折する際は二段階右折をする必要があるので、通勤距離が10Kmぐらいまで人におすすめです。
また、非力なので坂道が多い場合はパワーのある原付二種の方が無難です。
必要な免許は原付免許で、16歳以上で取得可能となります。
原付免許は、住民票のある都道府県の運転免許試験場や運転免許センターで学科試験を受けることで取得できます。
原付二種の特徴
原付二種は、排気量50ccを超え125cc以下の二輪車が該当します。
法定速度は時速60kmまでとなっているので、通勤距離が長めであったり、 幹線道路を使う人におすすめです。
原付一種とは異なり二人乗りが可能で、二段階右折も不要となります。
ただし、高速道路や自動車専用道路は走行不可です。
原付二種の免許(小型限定普通二輪免許/AT小型限定普通二輪免許)も、16歳以上であれば取得できます。
免許の取得方法は、教習所に通う方法と運転免許試験場で直接受験する方法があります。
教習所を利用する場合は費用が高くなりますが、合格率が高く、短期間で取得しやすいのが特徴です。
試験場での一発試験は費用が安いものの、合格率が低いため、複数回受験する場合は総費用が増える可能性があります。
ステップ②:自分に合ったバイクを選ぼう

バイクはメーカー直営店、バイク専門店、中古販売店などで購入できます。
バイクのタイプは大きく分けて「オンロードモデル」、「オフロードモデル」、「スクーター」の3種類があります。
通勤・通学では、AT(オートマチック)で操作が簡単なスクーターがおすすめです。
シート下には収納スペースがあるので実用性が最も高いです。
しかし、乗りたいバイクがある方や、週末ツーリングを楽しみたいという方は、オンロードモデルやオフロードモデルのバイクでも構いません。
やっぱり乗りたいバイクに乗るのが一番ですからね。
スクーターの特徴
スクーターは、クラッチ操作やギアチェンジが不要なため、車で言うオートマのような感覚で初心者でも簡単に運転できます。
また、シート下やフロントのインナーパネルなどに収納スペースがあり、通勤・通学や買い物に便利です。
- タクト(ホンダ)
- JOG(スズキ)
- ビーノ(ヤマハ)
オンロードモデルの特徴
オンロードモデルは、舗装された道路を快適に走行するために設計されたバイクの総称で、エンジンやサスペンション、タイヤなどが舗装路向けに最適化されています。
種類やデザインも豊富にあり、さらに細かく以下の種類に分かれます。
- ネイキッド:カウル(風防)がなくエンジンやフロントがむき出しのシンプルな構造。教習車としても使われる万能タイプ。
- スーパースポーツ(SS):カウルで覆われ、高速走行や旋回性に優れたレーサーレプリカタイプ。
- ツアラー:長距離ツーリング向けで、風圧を減らすカウルや快適な乗車姿勢を備える。
- クラシック/ネオクラシック:レトロなデザインで趣味性が高い。
- アメリカン(クルーザー):低く長い車体、ゆったりした乗車姿勢でのんびり走るのに適している。
原付二種では、原付一種よりもデザインの選択肢が多いです。
- スーパーカブ(ホンダ)
- GSX-R125(スズキ)
- XSR125(ヤマハ)
オフロードモデルの特徴
オフロードモデルは舗装されていない悪路や山道、林道などを走ることを想定したバイクで、車高が高く脚周りのクリアランスが大きいのが特徴です。
オフロードバイクは走破性を重視するほど公道性能は犠牲になりやすく、用途に合わせて選ぶ必要があります。
主なオフロードモデルの種類は、次のようなものがあります。
- オフロードバイク:未舗装路向けのタイヤと車体。
- モタード:オフロード車にオンロードタイヤをつけたタイプで、オン・オフ両方走れる。
- アドベンチャーバイク:オンロードとオフロードの両方を走れるモデル。
- CT125 ハンターカブ(ホンダ)
- KLX125(カワサキ)
- XTZ125(ヤマハ)
ステップ③:バイク保険に加入しよう
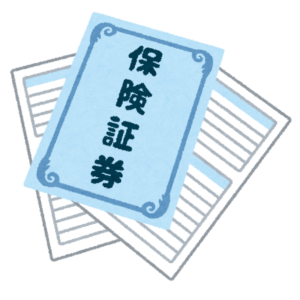
バイク保険には「自賠責保険(強制保険)」と「任意保険」の2種類があります。
自賠責保険は最低限の保障ですので、任意保険もセットで入りましょう。
自賠責保険(強制保険)
バイクを含むすべての自動車に加入が義務付けられている保険です。
対人賠償のみを補償し、事故の被害者を最低限救済するためのものです。
補償範囲が限定的で、対物賠償や自分自身のケガ・バイクの損害は補償されません。
自賠責保険の加入手続きは、バイクの販売店、保険代理店、損害保険会社の営業所、コンビニなど多くの窓口で即日加入が可能です。
原付バイク(125cc以下)の自賠責保険の保険料は、法律で定められている保険なので、どの保険会社で契約しても保険料は同じです。
契約期間は1年から5年まで選べて、残りの保険期間が1ヶ月以上であれば、解約返還保険料が支払われます。
長期契約するほど、一年にかかる保険料が割安になります。
| 保険期間 | 保険料 | 1年あたりの保険料 |
|---|---|---|
| 1年 | 6,910円 | 6,910円 |
| 2年 | 8,560円 | 4,280円 |
| 3年 | 10,170円 | 3,390円 |
| 4年 | 11,760円 | 2,940円 |
| 5年 | 13,310円 | 2,662円 |
任意保険
任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分を補償します。
主な補償内容は以下の通りです。
- 対人賠償(無制限が主流)
- 対物賠償(無制限が主流)
- 搭乗者傷害、人身傷害
- 車両保険(盗難補償含む場合もあり)
- ロードサービスや示談交渉サービスなど
保険料の目安は保証内容で変わりますが、年間で11,000円から60,000円です。
ダイレクト型(ネット型)保険を選んで、複数社の見積もりを比較することで保険料を安く抑えることができます。
もしくは、自動車を所有している場合は、自動車保険のファミリーバイク特約を付帯できます。
運転者の年齢やバイクの台数に関わらず、家族全員が補償対象になるのでコストパフォーマンスの高い保険特約です。
ステップ④:必要な装備・グッズをそろえよう

バイク通勤・通学を快適かつ安全に続けるためには、「装備」がとても重要です。
ここでは必須アイテムから、あると便利なグッズについて詳しく紹介します。
ヘルメット
ヘルメットは法律で着用が義務づけられているだけでなく、自分の命を守る最も大事な装備です。
国内で販売されるヘルメットには「PSCマーク」の貼付が義務付けられています。
日本の法定基準で、最低限の衝撃吸収性、耐貫通性、あごひも強度などの試験をクリアしています。
より高い安全性を求めるなら「SGマーク」や「JIS規格」などの安全基準をクリアしたものを選ぶようにしましょう。
ヘルメットは、用途や安全性、快適性に応じてフルフェイス、ジェット、ハーフなどの種類に分かれています。
安全性を重視するならフルフェイスが最適ですが、用途やスタイルに合わせて選びましょう。
レインウェア
雨の日も通勤するなら、レインウェアは必須です。
選び方のポイントは、上下セパレート型で耐水圧20,000mmのものです。
耐水圧とは、生地がどれだけの水圧に耐えられるかを示す数値です。
数値が高いほど生地が水を通さない性能が高いことを意味して、耐水圧20,000mmでは嵐でも耐える事ができます。
さらに夜間の走行を考えると、反射材付きのものを選んでおくと視認性が上がって安心です。
雨の日は靴の中まで濡れることも多いのでシューズカバーや、防水グローブを合わせて使うのもおすすめです。
バイク用グローブ
冬の寒さ対策であったり、転倒したときに手を守るためにグローブの着用も必要です。
春や秋は通気性がありながらプロテクターが付いたものが適しており、冬場は防風・防寒に特化したものを選ぶことで快適に走行できます。
夏は涼しさ重視のメッシュグローブが便利ですが、最低限のプロテクションがあるものを選びましょう。
リアボックス
スクーター以外のバイクは荷物の積載性が皆無なので、リアボックスを取り付けると便利です。
容量が45L程度あれば、フルフェイスのヘルメットとレインウェアは十分入ります。
バイクで通勤・通学をしていると、突然、雨が降ってくることもあるので、レインウェアはリアボックスに常備しておくと安心です。
防寒グッズ
バイクは風を直接受けるため、冬場の走行はかなり冷え込みます。
ネックウォーマーで首周りをまわりをしっかりガードして、ハンドルカバーや防寒グローブで手の冷えを防ぎましょう。
最近では電気の力を使って発熱し、素早く暖めることのできる電熱ジャケット、グローブ、パンツなどのアイテムが充実しています。
寒い冬でも電熱ウェアを活用すると快適になります。
まとめ
以上、バイク通勤・通学を始めるための4ステップを紹介しました。
- 免許の取得
- 自分に合ったバイク選び
- 適切な保険加入
- 必要な装備の準備
この手順を踏めば、安全・快適にバイク通勤を始めることができます。
バイクの魅力は、通勤や通学だけでなく、近所への買い物や週末のツーリングなど、日常にちょっとした“楽しさ”をプラスしてくれることです。
ぜひ、あなたもバイク通勤ライフを始めてみませんか?